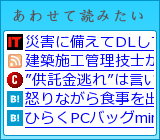2008-12-01 [長年日記]
_ [Jazz] Things That I Used To Do / Joe Turner
個人的事情で図体のでかい人には何となく親近感があるのだが、ビッグ・ジョー・ターナーは図体もでかかったが音楽家としても器量のでかい人だった。
歌手としての技量という点ではいろいろ限界もあったはずで(大体どの曲も同じキーで歌っている)、そもそも楽譜が読めたかどうかすら怪しいものだが、シャウターの名にふさわしい馬鹿でかい声量とここぞというところにシャウトが決まるタイミングの良さ、どんなセッティングでも何となく自分の色の染め上げてしまう個性、加えてマディ・ウォーターズらと同質の揺るぎなき威厳とそこはかとなく漂うユーモア、といったターナーならではの美質が補って余りある。特に驚かされるのはその柔軟性で、元は戦前から活躍するブルーズ屋さんなのに戦後から1950年代にかけてもR&Bや初期のロック・チャートでヒットを連発、結果として、ブルーズやジャズのみならず、ロックンロールの創始者の一人という称号をも手に入れることにもなった。
チャートゲッターという意味では1950年代末くらいにほぼ終わっていたターナーだが、1970年代に入るとノーマン・グランツが興したパブロ・レーベルに入って(記憶が確かならば実はターナーが専属アーティスト第一号だったはず)主にジャズ系の人々を従えた録音を大量に残すことになる。どれもこれもいかにもパブロ(というかグランツ)の仕事らしい、プロデュースという概念がほとんど存在しないようなジャムセッションもので、参加した顔ぶれも超一流から聞いたこともないような人まで種々雑多、結果として出来も玉石混淆という何とも曰く言い難いものだが、私はどれも好きで良く聞いている。ターナーはいかにも大物という感じで、とりあえずひとくさり歌ったら俺はお役御免、後は他の奴に好きに吹かせてやろうとでーんと構えている(たぶん手を腰に付けてひょこひょこ動かしながら)という風情が好ましい。別にターナーに限らず、昔のミュージシャンは個性が強いというか味が濃いので、こういう作り方をしてもちゃんと音楽として成立しうるのですね。もちろんうまくいかないケースもあるけれど…。
今回取り上げたのもそうしたパブロのターナー・ジャムの一枚で、小粒とは言えそこそこ豪華なメンツを集めて、レパートリーもギター・スリムのあれやビリー・エクスタインのあれを含み、音楽的にもうまく行っているほうだと思う。トランペットのブルー・ミッチェルの存在が特によく利いているが、何せテナーにワイルド・ビル・ムーア(マーヴィン・ゲイの『ホワッツ・ゴーイン・オン』で印象的なサックスを吹いていたベテラン・ホンカー)、アルトにエディ・クリーンヘッド・ヴィンスン、ピアノに西海岸R&Bの大ベテランであるロイド・グレン、オルガンになぜかギルド・マホネス(!)というなかなかの陣容である。だが、たぶんこのセッション成功の本当の功労者は、セロニアス・モンクのベーシストとして有名なラリー・ゲイルズと、ハービー・マンのバンドにいたドラムス、ブルーノ・カーの二人だろう。この二人ががっちり音楽を下支えしているので、上でおっさんたちが好き放題に歌って弾いて吹き倒してもぐだぐだにならず何とかなるのですね。どこまで事前にアレンジしたのか知らないが、随所に入るリフがバシッと決まっていて、まるでターナーが小型ビッグバンドを従えて歌っているかのような感じですらある。個人的にはどうせヴィンスンを呼んできたならターナーと一曲くらいデュエットで歌わせれば良かったのにと思うのだが、それは無い物ねだりということですか。